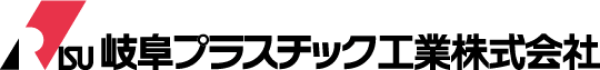2025.07.28
コストと環境を両立する梱包資材──トライウォールの魅力と限界、そして次なる選択肢

物流・包装資材において、近年ますます重視されているのが「環境配慮」と「コスト削減」の両立**です。脱炭素社会への移行やSDGsの推進を背景に、使い捨て資材の見直しや、輸送における省エネルギー化が求められるようになってきました。
こうした流れの中で注目されてきたのが、強化ダンボールの一種「トライウォール」です。従来のダンボールよりもはるかに高い強度を持ちながら、木箱のような重量物に比べてはるかに軽く、しかも再生紙を原料としたリサイクル可能な素材であることから、国内外を問わず多くの物流現場で導入が進んできました。
トライウォールは、三層以上の波形紙と平面紙を組み合わせた多層構造によって、高い耐圧強度・衝撃吸収性を実現しており、たとえば精密機器や美術品、電子機器など破損リスクの高い製品の輸送において高い評価を得ています。また、軽量性による輸送費の削減効果も大きく、空輸や海上輸送といった長距離の国際輸送においては、木材や樹脂素材よりもコストパフォーマンスに優れるケースが多く見られます。
このようにトライウォールは、高い保護性能・軽量性・環境配慮を兼ね備えた次世代の紙系梱包材として、これまで数多くの企業が「梱包材の最適解」として採用してきた実績があります。
しかし、近年の物流環境や品質管理の要請が高度化する中で、課題も見え始めています。
本記事では、トライウォールの特性と採用理由を改めて整理したうえで、その限界や代替素材としての可能性を「岐阜プラスチック工業のテクセル」と比較しながら解説します。
なぜ多くの現場が「トライウォール」を選んできたのか?
強化ダンボールの進化形──トライウォールとは?
トライウォールは、三層構造の波形紙を組み合わせた、いわゆる「超強化ダンボール」です。一般的なダンボールと比べ、
- 高い耐圧・耐衝撃性
- 木箱より軽量で取扱がしやすい
- リサイクル可能で環境配慮型
- 保管や輸送のコスト削減に貢献
という特長を持ち、輸送コストの削減と環境配慮の両立を実現できる梱包材として多くの企業で採用されています。
紙系梱包材「トライウォール」が抱える3つの現場課題
湿気・水濡れに弱く、梅雨・海外輸送で破損リスク
トライウォールの最大の弱点は、湿気や水濡れに弱いことです。防湿加工を施しても限界があり、特に梅雨時や海上輸送では紙が吸湿し、強度が著しく低下することがあります。
強度は高いが、点荷重に弱く破れやすい
面に対する圧には強くても、角や点での衝撃に弱いという構造上の課題もあります。長距離輸送や多段積みの現場では、製品の破損リスクが見過ごせません。
再利用が難しく、長期的にはコストがかさむ
紙素材ゆえに繰り返し使用が難しく、湿気や衝撃で劣化しやすいため、使い捨て前提の運用になりがちです。初期費用は抑えられても、長期的なコストや環境負荷が増すというケースも少なくありません。
岐阜プラスチック工業の提案──高機能素材「テクセル」で根本解決

岐阜プラスチック工業では、こうした課題に対して、プラスチックハニカム構造材「テクセル」を用いた提案を行っています。
テクセルとは?
テクセルは、ポリプロピレンをベースにしたハニカム構造の中空ボード素材で、軽量かつ高剛性・耐水性・耐薬品性を兼ね備えています。
・水濡れや湿気の影響を受けない
・耐衝撃性が高く、破損しにくい
・繰り返し使用でき、再利用性が高い
・異物混入が起きにくく、衛生的
物流現場の「実用性」を追求した設計
トライウォールでは対応が難しかった濡れた環境・清潔性が求められる現場でも、テクセルなら安定した性能を発揮します。
たとえば以下のような現場課題に対応しています:
- 海上輸送時の結露・塩害による梱包崩壊
- 食品や医薬品における異物混入リスク
- 倉庫内での湿気・カビによる廃棄ロス
初期費用はやや高くとも、長期的にコスト削減
一見すると単価は高く見えるかもしれませんが、数十回単位で繰り返し使える耐久性や、破損・返品リスクの削減まで含めると、トータルではむしろ大幅なコストダウンにつながります。
物流現場の「構造的な課題」を、資材で解決する
岐阜プラスチック工業のスタンス──売るのは「資材」ではなく「改善提案」
私たちは単に「テクセルという製品を売る」のではなく、現場の悩みや制約に応じて最適な物流設計を一緒に考えるスタンスを大切にしています。
- スペースが狭くパレット運用が難しい
- 濡れた環境下でも清潔に保ちたい
- 自動搬送装置(AGV)対応の梱包材が欲しい
こうしたお客様の声に耳を傾けながら、テクセルをベースにしたカスタマイズ設計や最適サイズの提案など、「運用」まで含めた改善支援を行っています。
導入事例──繰り返し使えて、現場が変わる
CASE① 海外輸送+梅雨対応に

メーカーでは、これまで輸出梱包材としてトライウォール製の強化ダンボール箱を使用していました。
しかし、海外の倉庫で長期間保管されるケースが多く、湿気によって箱が劣化してしまい、箱の底抜けや側面の膨れが頻発。さらに、輸送時の段積みによって箱が潰れ、製品が破損して返品となるトラブルが増加していました。特に海上輸送では塩害や結露の影響もあり、安定した品質管理が難しいという課題を抱えていました。
そこで導入されたのが、岐阜プラスチック工業の「テクセル」製梱包材です。テクセルは湿気や塩害に強く、長距離輸送や長期保管でも箱の形状や強度を維持。導入後は、輸送中の破損・返品はゼロを達成しました。
さらに、紙素材と異なりテクセルは繰り返し使用が可能なため、従来は使い捨てだった資材を何度も再利用できるように。結果的に梱包資材にかかる年間コストを約40%削減することに成功しました。
こうした改善により、品質の安定だけでなく、環境負荷軽減やコストダウンといった多面的な効果が実現しています。
トライウォール使用時:
- 海外倉庫での長期滞留時、湿気で箱が劣化
- 段積みによる箱潰れが発生し、破損返品が増加
テクセル導入後:
- 湿気や塩害にも強く、破損・返品ゼロ
- 複数回使用可能で資材費も約40%削減
CASE② クリーンルームでの梱包資材見直し

ある精密機器メーカーでは、クリーンルーム内で使用する梱包資材としてトライウォール製の箱を使用していました。しかし、紙素材特有の「紙粉(ペーパーダスト)」が発生し、製品への異物混入リスクが指摘されるようになりました。
さらに、トライウォールは水拭きやアルコール清掃、滅菌処理ができないため、衛生管理上使い捨てを前提とした運用を強いられており、資材コストの増加と産業廃棄物の処理負担が課題となっていました。
そこで新たに採用されたのが、プラスチック製ハニカム構造材「テクセル」です。テクセルは表面が滑らかで毛羽立ちがなく、紙粉が発生しないうえ、洗浄や消毒にも対応可能。クリーンルーム内でも再利用が可能な資材として評価されました。
その結果、検査工程での「紙粉対策」や「異物混入チェック」などの煩雑なフローを見直す必要がなくなり、業務効率も大幅に改善。衛生基準を保ちながら、コストと手間の両面で改善効果が得られています。
トライウォール使用時:
- 紙粉の混入リスクが課題に
- 清掃・滅菌ができず廃棄前提
テクセル導入後:
- 洗浄して再利用、衛生基準をクリア
- 検査工程の再構築が不要に
まとめ──「素材選び」は、物流戦略の第一歩
コストだけを見れば紙製の梱包材は魅力的に映るかもしれません。しかし、実際の現場で生じる湿気・破損・クレーム・再購入・人的負担までを含めて考えれば、選ぶべきは「課題を減らす素材」です。
テクセルは、岐阜プラスチック工業が長年培った物流ノウハウをもとに開発された、まさに「課題解決型梱包材」。
- 長距離輸送における安全性
- AGV対応など省人化施策との相性
- 繰り返し使える環境負荷軽減素材
これらを備えたテクセルは、これからの物流現場において、「単なる梱包材」ではなく「戦略資材」として活躍します。