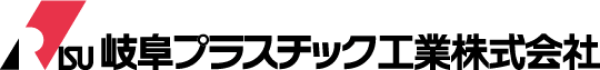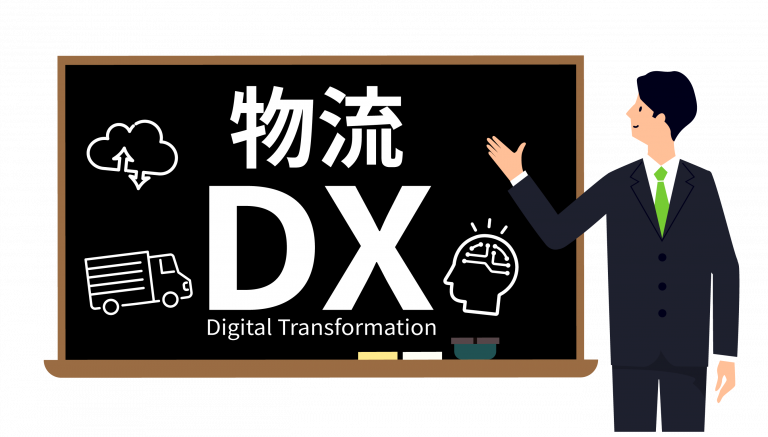2025.07.28
環境対応と物流効率化を両立する、岐阜プラスチック工業の戦略とは?

複雑化する物流の現場──法改正と社会的要請が迫る転換
2024年問題に代表されるように、物流現場はいまかつてない変革期を迎えています。ドライバー不足や高齢化、再配達増加などによって、 “運べないリスク”が企業活動そのものに影を落としつつあります。
さらに、2025年4月1日に改正・施行された「物資の流通の効率化に関する法律(物流効率化法)」および関連する貨物自動車運送事業法も同日から施行済となりました。この改正では、荷主・物流事業者に対して、荷待ち時間や荷役時間の短縮、積載率の向上などの取り組みが努力義務化され、一定の規模以上の「特定事業者」には、中長期計画の作成・提出、物流統括管理者の選任も義務化されています。
つまり、これまで“現場任せ”にしてきた物流業務が、今や経営層主導で戦略的に管理すべき重要な経営課題へと格上げされたわけです。
この背景には、ESG経営やScope 3温室効果ガス排出量開示の拡大があり、物流現場には「効率化」と「持続可能性」の同時達成が強く求められています。
岐阜プラスチック工業は“資材メーカー”を超えた課題解決企業へ
岐阜プラスチック工業は、これまで「樹脂製パレット」や「コンテナ」などを中心とした資材開発・製造に強みを持つ企業でした。しかし現在は、こうした製品単体の供給に留まらず、物流効率化と環境配慮を同時に支援するトータルソリューションの提供企業へと進化を遂げています。
その代表的な製品が以下の通りです:
| 製品名 | 主な特長 | 効果・用途例 |
| リサイクルシリーズ | 再生ポリプロピレン材を用いた高耐久資材 | Scope1〜3までの**CO2削減効果(最大38%)を明示 |
| パレットレンタル | 管理・回収不要、着払返送が可能な標準化資材サービス | 資材共有・共同輸配送支援に最適 |
| TECCELL(テクセル) | ハニカム構造を活用した軽量・高強度な樹脂素材 | モーダルシフト、重量制限対策、脱炭素物流に有効 |
| Fボックス・スリーブボックス | 折りたたみ式輸送容器 | 戻り便削減・保管スペース削減・積載効率向上に貢献 |
これらは単なる製品ではなく、物流の流れそのものをデザインし直す発想から生まれたものです。
物流効率化で得られる3つの大きな成果

積載効率の向上
物流における積載効率の向上は、燃料消費の削減や輸送コストの低減に直結する重要な要素です。具体的には、車両の積載計画の最適化やパレット配置の工夫などの技術や手法が活用されます。これらの取り組みにより、1回の輸送でより多くの貨物を効率的に運ぶことが可能となり、結果として物流全体のコストパフォーマンスが向上します。
積載効率を高めるための主な方法には以下のものがあります:
- 積載計画の最適化:貨物のサイズや重量、優先順位を考慮し、車両内での配置を最適化する。
- パレット配置の工夫:パレットの種類や配置方法を工夫し、スペースを最大限に活用する。
- 積載管理システムの導入:リアルタイムで積載状況を管理し、効率的な積載をサポートする。
これらの手法を実際に導入した企業では、積載効率の向上により年間で約15%の燃料費削減と、輸送コストの10%削減を達成しています。例えば、某物流企業では積載計画の最適化を行うことで、車両1台あたりの貨物運搬量を20%増加させ、全体の配送回数を削減しました。これにより、環境負荷の低減にも大きく寄与しています。
空気を運ばない物流設計
積載率の低さは、日本の物流における構造課題のひとつです。トラックの**片道輸送(空荷)率は約40%**と言われており、これは燃料・人件費・CO2排出すべての無駄に直結します。岐阜プラスチック工業では、「パレットの標準化」と「積載設計の最適化」を重視しています。
| 製品・サービス名 | 特長・機能 | 効果・活用目的 |
| リスパレット シリーズ | 高荷重対応・製品寸法の標準化設計 | 混載効率の向上、積載の安定性向上 |
| スリーブボックス/Fボックス | 段積み対応・折りたたみ可能な輸送容器 | 往復効率の改善、保管スペース削減に貢献 |
| 積載率最適化コンサルティング | 積載テスト・搬送シミュレーションの個別対応 | 積載率の最大化・燃料コスト削減を実現 |
こうした取り組みにより、導入企業では輸送回数を20%削減し、燃料費・配送人件費の大幅削減を実現しています。
荷待ち・荷役時間の短縮──ドライバー負担軽減と回転率向上
物流拠点における「荷待ち時間」や「荷役作業の遅延」は、ドライバーの拘束時間を長引かせるだけでなく、配送スケジュールの乱れや運送コストの増加、さらには現場の人的負荷やストレス増加にも直結する深刻な課題です。特に近年では、2024年問題を背景に、ドライバー1人あたりの稼働時間が制限される中、「待機時間の短縮」は喫緊の改善ポイントとして注目を集めています。
具体的な方法としては、以下のような戦略が挙げられます。
- 荷役システムの自動化: 自動化された荷役設備を導入することで、手作業による時間のロスを削減し、作業の迅速化を図ります。
- スケジューリングの最適化: 効率的なスケジュール管理を行い、トラックや荷物の適切なタイミングでの配車を実現します。
- リアルタイムデータの活用: IoTデバイスやデータ分析を活用して、荷待ちの状況をリアルタイムで把握し、迅速な対応を可能にします。
こうした現場課題に対し、岐阜プラスチック工業では、現地でのヒアリングを起点としたソリューション設計を重視。実際の作業環境や物流導線を細かく分析した上で、作業時間を短縮し、誰でも簡単に扱える資材提案を行っています。
岐阜プラスチック工業 製品サイトはコチラ
これらの資材には共通して、「誰でも安全に・効率的に扱える設計思想」が貫かれており、作業者のスキルや体力に依存しない、属人性のない現場づくりに貢献しています。実際の導入企業では、これらの取り組みによって、平均で荷待ち時間を約30%削減、配送トラックの回転率を約25%向上させる成果が報告されています。これにより、現場負担の軽減だけでなく、企業全体の配送効率・人件費・燃料コストの最適化にも大きく寄与しています。
Scope3対応とCO2削減の「見える化」
現在、上場企業や大手製造業を中心に、サプライチェーン全体の温室効果ガス排出量(Scope3)の開示が急速に広がっています。
こうした中で、物流部門におけるCO₂排出の“見える化”と削減施策は、調達評価や取引継続の前提条件となりつつあります。
岐阜プラスチック工業では、CO2排出量の可視化に対応した製品群として、「環境-1_リサイクルシリーズ」を展開。原材料〜使用〜廃棄・リサイクルに至るまでのLCA(ライフサイクルアセスメント)を開示し、最大38%のCO2削減効果を明示しています。
さらに、自治体や国の補助金・優遇税制に適合する認定素材・設計も多く、制度活用と環境配慮を両立することが可能です。企業のCSR・ESG対応をサプライチェーン全体で支える。その“縁の下の力持ち”として評価されています。
物流効率化法と制度対応の実践
2025年4月より施行される「物流の効率化に関する法律」では、以下のような実務義務が新たに加わります:
- 特定事業者に該当する場合、中長期物流計画を国に提出
- 積載率・荷待ち時間・CO2排出量の定期モニタリング
- 物流統括管理者の設置(現場レベルの責任者と経営層をつなぐ役割)
岐阜プラスチック工業では、このような制度変化にあわせて、資材や仕組みレベルからの対応支援を提供しています。制度対応というと「書類対応」や「経営層向け資料作成」が先行しがちですが、実務を担う現場に寄り添った“現実解としての資材改善”の支援が可能です。
脱炭素化と輸送最適化──TECCELLによるモーダルシフト支援
「鉄道・船舶輸送への切替=モーダルシフト」は、国土交通省も推進する脱炭素物流の柱ですが、現実にはハードルも少なくありません。特に課題となるのが、「重量」と「強度」の両立となり鉄製パレットや木箱では、輸送重量が嵩み、鉄道コンテナの最大積載量を圧迫してしまいます。
この問題を解決するのが、ハニカム構造樹脂素材「TECCELL(テクセル)です。
- 従来比で約1/3の重量
- 高い耐圧・耐衝撃性能
- 防湿・防錆・断熱など、多様な保護機能
また、折りたたみ・再利用も可能な設計により、保管・戻り便問題にも対応。
鉄道輸送・海上輸送において、費用・環境・オペレーションのバランスを取れる最適解として、導入企業が増加しています。
まとめ──「資材を変える」ことで物流全体が変わる
「物流課題」と聞くと、多くの方が“配送ルートの見直し”や“倉庫システムの刷新”など、大規模でコストのかかる変化を想像するかもしれません。しかし実際には、日々の業務で使うパレット・コンテナ・仕分け資材を変えることが、物流の最初の変革点になります。
岐阜プラスチック工業は、単なるモノ売りではなく、「物流の効率と環境の両立」を実現する資材提案会社です。
- 脱炭素を推進したい
- 制度対応を進めたい
- 現場の負担を減らしたい
- 長期的な物流戦略を描きたい
そうした想いを持つ企業様と、共に物流の未来を描き、持続可能な社会の実現に貢献していきたいと私たちは考えています。
まずはお気軽に、お問合せ・無料相談をご活用ください。